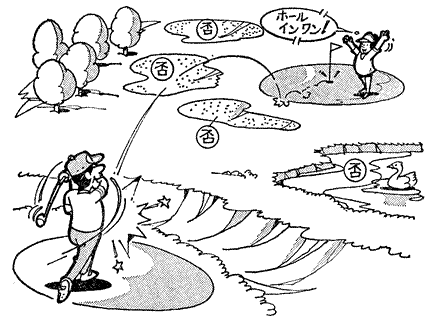
電脳経済学v3> g自分学> 1-4 人はいつのまにか天職についている
電脳経済学v3> g自分学> 1-4-1 自己実現とは自分になりきること
ソクラテスは何か困ることがあったとき、ダイモニオンという像にその行く道についてうかがいをたてることをつねとしていました。ところが、このダイモニオンはいつも「否」という言葉しか答えなかったということです。
このことは示唆に富みます。もし“よろしい”という肯定的な答であれば、残された可能性はそこで閉ざされてしまいます。筋道だったうかがいに対して、そのつど「否」という言葉が返ってくるとしたら、誰しも知恵をしぼって次の方法を考えざるを得ません。その結果、問題はおのずからあるところに収束していくはずです。ダイモニオンは物事にきわまりがないことをつげるとともに、人間の知恵が足りないことを指摘しているように思われます。
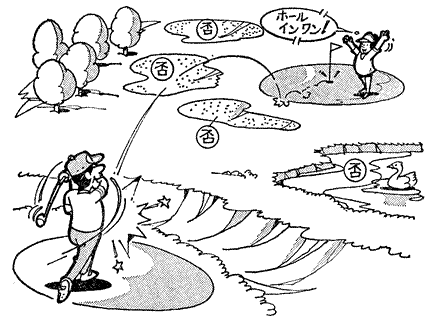
私たちの周辺でも法律であれ、道徳であれ、今では貴重な存在となった頑固親爺であれ「……するべからず」「汝……するなかれ」「これもだめ、あれもだめ、だめといったらみんなだめ」といった調子で、すべてが「否」です。それでは私たちの活動の範囲がなくなるのかといえば、まだ結構残っています。このような制約を課することによって、一定の確かた領域が定義されることとなります。
このようなたゆまぬ否定ののちに、否定し得ない何物かが残ります。「命」「生」「美」「信」「愛」「善」「神」「仏」「真」「聖」「和」これらがそれです。時代や場所を超えた価値という意味で、これらは「最高価値」あるいは「普遍的価値」とよばれています。
私たちはダイモニオンをしても否定し去ることのできない、これらの価値を人格の根底に据えおくことによって、人生をゆるぎないものとすることができます。
「人は何をなすべきか」「人は何をなしてはならぬか」これは人のふみ行うべき道を示すもので倫理とよばれるものです。私たちはこのことについて、すでに大まかに知っています。
それにもかかわらず、日常態としての私たちは往々にして「人は何をなすべきか」をよくせず、「人は何をなしてはならぬか」の方に傾いていきがちです。このことを仏教では「業」と称し、キリスト教では「罪」とよびます。思うにまかせぬ自分の姿です。私たちの意識は生涯を通して、この間を揺れ動きながらも、ついには本来態としての「私は何をなすべきか」の道を歩むように思われます。これは同時に「私は何をなしてはならぬか」という“抑制”と相呼応しながら方向づけられていきます。さらに他者による否定である“制約”がこの外側で大きく作用していることも見逃すわけにはいきません。
この究極的な人生目標が形成されていく過程で、往々にして異物がまぎれこみがちです。その異物は心のゴミともムシともいわれますけど、より広い意味で「煩悩」とよばれるものです。それは私たちの性格を強くする働きがある反面、人間的な成長に限界を与えるものでもあります。たとえば「憎しみ」がそれに相当します。憎しみは金属的かつ鋭角的な激しさをもって対象に迫っていきます。
自身で意識するしないは別として、人は誰でも社会に対してある種の憎しみをもっています。憎しみとは遺恨の念が抑圧されて復讐心となったものです。私たちが努力、勤勉あるいは信念とよんでいる美徳は実は偽装されたもので、その裏にはこの復讐心がうごめいているのです。つまり、美徳は心の奥底で悪徳によってかきたてられ、後押しされています。このような人間心理に潜む心のしこりはコンプレックスとよばれるものです。
先に最高価値としてあげた“善なるもの”は、それ自身漠然とした存在です。加えて発散的な性格をもつものです。それに対して“悪たるもの”は、はっきりした姿があり、その上収束的傾向があります。善は散らばりやすく、悪はまとまりやすいという性質があるようです。
自己否定とはこのまぎれこんだ異物を丹念にとり除くことであり、自己肯定とはこの散らばりやすい善きものをつなぎとめ、自己の意志をもって管理することといえます。このことによって自己実現がより確かなものとなります。
社会は広大な網をそれぞれの主張の方向に、綱引きをしているようなものです。ある人たちが引っ張れば、他の人たちは引きずられながら、社会全体としては一定の方向に進んで行きます。
全員参加による自己主張の大合唱は、健全な社会の証であり、大いに歓迎されるところです。持場を守るために、立場を主張することがなければ、人間の相互理解も社会全体の進展もあり得ません。
この場合、反対者の存在はとりわけ意味深いものがあります。もし反対者がいなくて、すべてが自分の思う通りになるとすれば、それは味気ない人生となるのみならず、どうしても方向を誤ってしまいます。私たちは反対者の存在を通して、考え直す機会が与えられているのです。そのことによって、ついには真実の自分に目覚めることができるとともに、社会全体としても、より正しい方向に進むことができるのです。
現代の日本は、世界でもまれにみる開かれた社会です。政治家はその主張を表現することによって“広く”国民の支持を得たいと願っています。芸術家は創作活動を通して白已を表現しています。そのことによって自身の芸術性が“深く”理解されることを願うからです。
私たちはこの“広がり”とも“深み”ともさして縁がない平凡な存在かも知れません。しかし、誰もが隠れた才能を世界に示したいという要求をもっています。そのために銘々に役割がわりふってあるのです。自己表現を通して自己を主張し、社会に認められたいと願うのは、人間感情の自然な発露であり、生命の流れともいえるものです。
社会はこの自己を表現する人とそれを評価する人から成り立っています。つまり内から外へ向けて自己を表現する人と、外にあってそれを受けとめて評価する人を必要とします。評価は再び外から内へと本人に帰っていきます。この意味で自己実現とは同時に他者実現でもあります。これが社会に対する貢献にほかなりません。私たちはこのことによって、自己をいくらかでも永遠なものとすることができるのです。
私たちの意識は、自我を中心として一貫した統合性をもっています。さらにある程度の安定性を保っています。これ故に私たちは一個の人格として認められています。しかし人間は内在する可能性を実現するため、この安定性を崩してさえ、より高次の統合性に向う傾向があります。スイスの精神医学者ユングは、このようにより高次の全体性を志向する努力の過程を、自己実現とよび、これを人生究極の目的としました。ユングはまたこれを個性化の過程ともよびました。
ところが、この自己実現は直線的に達成されるとはいえません。誰もが自身の生き方に確信をもっているわけではありません。春秋に富む、裏を返せば人生経験において未熟な、若い人の場合、ことにそのことがいえます。未来に対する不安ゆえに、自分に理解を示してくれる仲間を必要としています。仲間同志の相互理解を通して感情を共有し、もって共通の目標に向けて進むことができます。人間にはそれぞれ同質の部分と異質な部分があって、しかもそれが絶えず流動しています。つまり、物事を固定的に捉えることなく、同質のものは安定ないし力として働き、異質のものは発展ないし価値を与えるものと理解する必要があります。
「分け登る麓の道は多けれど、一つ高嶺の月を見るかな」という歌があります。私たちの人生において最終的な目標は同じであるとしても、そこに至る道は数多くあります。反対者の存在は別の方法があることを示しています。人間の悶着や葛藤はこの方法論の違いによるものです。
人はそれぞれ置かれている境遇や立場が異なっています。それは誰もが因縁とよばれる別々の過去を背負っていて、それから逃れることができないということです。その人の過去について理解が深まれば、その人がその方法によっていることにも合点がいきます。
私たちの心は外界の変化に対応して、極めて複雑な動きをしています。しかし、基本的に次のことはいえます。つまり、私たちの心は自我を中心とする意識と、それを支える無意識の相互作用によっていることです。無意識を代表するものが自己です。自我が自他峻別の総元締とすれば、自己は「万物斉同」の立場をとるものです。自分の内部で自我と自己が折合いよく、望むらくは自己の中に自我を包みこむような人生態度でありたいものです。