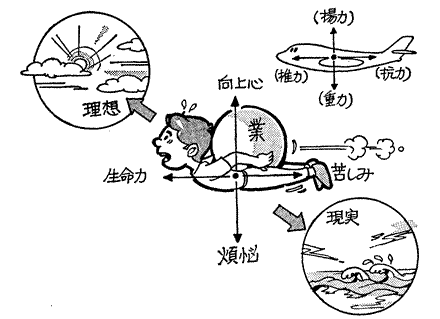
電脳経済学v3> g自分学> 3-2-3 人間とは業の塊とみたり
鳥のように自由に大空を飛びたいというのは人類永年の夢でした。ライト兄弟が初飛行に成功したのは二十世紀の幕開け、1903年のことですから、永い人類の歴史からみれば、それからごくわずかの期間で、人類はついに宇宙旅行ができるまでになりました。現在のところ、私たちは宇宙旅行というわけにはいきませんけど、飛行機ならば自由に乗ることができます。350トンもある巨大なジャンボが舞い上がり、時速千キロメートルで一万キロメートルの距離を無着陸で飛べるなど、ライト兄弟もあの世できっと驚いていることでしょう。これが人間の知恵の産物でないとすれば何でしょうか。
ところで飛行機がなぜ飛ぶかご存知でしょうか。初飛行一番乗りをねらう冒険野郎の命を救う目的もあったようですけど、当時におけるその道の学会は、空を飛ぶことは原理的に不可能であるから研究を中止するよう勧告を出したと伝えられています。事実、飛行原理は当時の科学水準では解明されていませんでした。飛行機は鳥が飛ぶような複雑な運動によって飛んでいるというより、むしろ凧が上る簡単な原理によって空を飛んでいるのです。ここが盲点でした。
凧は風があると上に昇る性質があります。水平に吹く風を受けて、それから上向きに働く力をとり出すのです。飛行機の場合は風まかせというわけにはいきませんから、その代り自分のエンジンによって推進力を生み出します。これを「推力」とよびます。水平定常飛行状態では、飛行機の重心に対して、水平、垂直方向に四つの力が働きそれが平衡しています。重心から前向きに「推力」が、後ろ向きに「抗力」が、上向きに「揚力」が、下向きに「重力」が働いています。あたかも止っているように静かな状態で飛び続けることができるのは、力学的にこの四種の力が釣り合っていることにほかなりません。
さてここで、大胆な想像力を働かせて、次の対応について考えてみましょう。「推力」は“生命力”に、「抗力」は“苦しみ”に、「揚力」は“向上心”に、「重力」は“煩悩”に、それぞれ相当するとしましょう。ここで、「飛行機」または「機体」が“業”に相当するものです。つまり“業”とは人間そのものになってしまうのです。このことが“業”という概念をきわめて理解しにくくしています。
人間はそれ自体分割も統合もできない統一体であります。しかし、もしその境地にとどまって、人間は分割不可能とすれば、人間は表現不可能となってしまいます。さらに、統合不可能の態度をとれば、同様に社会や自然と調和した存在となることはできません。人間の偉大さは、自分の意志でこの世界においてその部分となることも、全体となることも自由自在にできるところにあります。高いところに昇るばかりであれば、それは糸の切れた凧にひとしいもので、さしてこの世の役に立たないどころか、公害の源になりかねません。
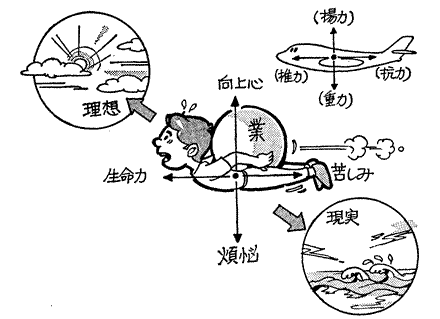
人間を理解しようとするとき、私たちは人間を一種の“集合体”とみなします。先に人間を「父母所成」「飲食所成」「意識所成」とする観点から定義しました。仏教の立場によれば、これはまた「三業」とよばれる「身業・口業・意業」にそれぞれ対応するものです。この三業についてもすでに述べました。身業が父母所成であることは容易に理解できます。次の口業は飲食所成に対応しています。口とは社会ないし環境に開かれた人間の開口部をさすものです。口業は身業と意業のインターフェイスの役割をはたしています。意業はそのまま意識所成です。これらの対応関係をまとめてみますと次のようになります。
人間の“業”とは
| 成因として | 父母所成 | 飲食所成 | 意識所成 |
| 三業として | 身 | 口 | 意 |
| 意識として | 知識 | 感情 | “意志” |
| 文化として | “肉体” | 社会 | 精神 |
| 飛行機にたとえれば | 機体 | 乗客 (荷物を含む) |
搭乗員 (機長で代表) |
| 日常用語で | 遺伝情報 (設計図) |
“業”務 (仕事、務め) |
“過去における |
| コンピュータ 用語として |
マシーン (ハードウエア) |
ジョブ (ヒューマンウエア) |
プログラム (ソフトウエア) |
説明がくどいのですが、これもまたいわゆる“業”のなせる“業”なのです。
まず人間の身体を生物学的にみれば、親から子、子から孫と体の形や性質が引きつがれていきます。この現象が遺伝であり、それはあたかもリレーで次々とバトンタッチがなされるように、生殖細胞を通じて遺伝情報が伝えられていきます。その中心的役割をになうものがデオキシリボ核酸(DNA)の分子構造で、いわば人体の“設計図”に相当するものです。綿々たる人間の神聖な営みも、いうならば原図からコピーをとっているようなものです。もっとも、生物の世界では原図よりコピーの方がよくなっていきます。これが進化です。過去の経験を生かして環境の変化に対応していく仕組みを、生物学では“進化”とよび、心理学では“無意識”と称し、仏教では“業”とするのです。
“業”とは基本的に、この“設計図”をさします。しかし、設計図に基づき完全な飛行機が製作されても、空を飛ぶことはできません。そこに機長をはじめ搭乗員が乗り組まないことには、さすがの文明の利器も金属の塊にすぎません。「仏作って魂入れず」の状態といえます。この搭乗員魂が“意識所成”です。この「意業」が業の中心をなすものです。
意識をさらに「知識」「感情」「意志」とわけると、そこにもやはり“意志”が中心に頑張っています。その“意志”なるものは“過去における行為の記憶”から出てくるようです。何をなしたか、何をなさなかったかの記憶と、意識野にある知識を相互につき合わせて、感情の流れとの関係から、最終的に“意志”が決定されます。いわば、父親、母親、先祖それぞれの代表者からなる三者会談によって自身の意志は決まることになります。意を座長とする知・情・意の三者会談ともいえます。
ここで“過去における行為の記憶”がくせ者です。未来の記憶などないし、行為のない記憶もありませんから、単に“記憶”としてもよいのですけど、ここはあえて“過去における行為の記憶”とした方が「意業」のフィーリングにマッチするのです。過去とは、宇宙開闢以降をさし、大体137億年位前からのことです。話が大きいのです。一方、サイズの方はぐっと小さく“極微”ですから電子顕微鏡でも見えない位こまかいのです。記憶が歳月の経過とともにうすれるように、業もまた小さくなっていきます。
“業”とは本来“行為”を意味します。行為とは行動のみならず、セックスも、考えることも、寝ることも、気絶することも、すべての動作を含みます。行為とは人間の生きている姿そのものをさします。人はそれに先だつ“過去における行為の記憶”に基づいて行為しています。現世に限らず前世やそのまた前世を含めてです。
人間の現在の行為は、本人が意識するしないは別として、過去の行為に支配されています。それはまた、現在の行為が未来を決定することを意味します。ただし、人間はその自由意志をもってこの過去業の支配を絶つことができます。人の一生は、過去の自分と現在の自分との間断なき壮烈な戦いにほかなりません。現在のこの瞬間は、私たちの全過去のアウトプットであり、同時に全未来に対するインプットであります。この瞬間この場所をおいて、この世界に働きかけることはできません。人は瞬間瞬間を丁寧に生きるしかないのです。
このことはまた次のようにいうこともできます。“それが良いことであれ、悪いことであれ、自分に関するすべての原因は自分から出て、その結果は早晩自分に帰ってくる”これが業思想の中心概念といえるものです。前段の“善悪判断”と後段の“因果関係”つまり“倫理”と“論理”の関係が車の両輪ならず、前輪と後輪のように一体化されるのです。アイツが悪いわけでもなく、社会が悪いわけでもなく、オマエさんが悪いんだよとお釈迦さんがゴツンと鉄槌を下されたわけです。この“自動鉄槌装置”が“業”であり、苦しみはそのセンサーといえます。
さて、これでやっと飛行機に搭乗員が乗りこみました。しかし、大切なものがまだ残っています。そうです。乗客と荷物です。そもそも、そのためにこの世に飛行機が存在するのですから、これは大変うかつでした。
「口業」は「飲食所成」に対応するものでした。生きるためには食べなくてはならない。食べるためには働かなくてはならない。「口業」とはその人の社会に対する窓口ないし出入口を意味するといえます。
この世に任務のない飛行機がないのと同様、私たちにもそれぞれ任務なり役回りが与えられています。それが業務であり、仕事であり、務めであります。学業に励む人、事業を起す人、家業をつぐ人、業績をあげる人、身過ぎ、世過ぎ、口過ぎ、生業(なりわい)のない人は誰一人としていません。生きている限り一人一人に宿命的な使命が与えられているとみなくてはなりません。それが天命です。これには誰も逆らうわけにはいきません。
徳川家康はその『人生訓』の冒頭に「人の一生は重荷を負いて遠き道を行くが如し、急ぐべからず」とさとしています。この重荷という“業”は私たちの背中にくくりつけられたものです。何としても逃れることはできません。それならいっそ、私たちは重荷を体の一部分とすればよいのです。そのことによって重荷ではなくなります。「厭離穢土」(えんりえど)「欣求浄土」(ごんぐじょうど)とは、この世とあの世のことではありません。厳しく自分自身を律する態度をさすものです。人間には、自身の意志をもって、自身の行為を選択する自由が与えられています。“人はその行為によってその人となる”のです。つまり、自己変革によってこの世がそのまま“穢土”から“浄土”になるのです。自分を変える力は自分にしかありません。仏教は終始一貫自分を問題にするのです。もし、それ以外の話がでてきたとしても、それはいわゆる“方便”にすぎないのです。“真実の自分に目覚める”どこまでいってもこれだけしかありません。